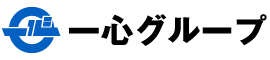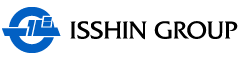一心通信建設(株)のスタート時の布陣は、代表取締役社長が私で、専務取締役に田中邑志、常務取締役に忠田光(故人)、以下、野村友幸、井上俊三、奥田昭彦、川重孝幸(故人)の4名が取締役であった。
つまり、創立メンバーの7名は全員が役員兼株主ということであった。
そして、創立時の私を今思い起こすと、6人の仲間から満場一致で会社の代表取締役社長という最高位をもらったものの、虚勢を張ることしかできそうにない自分自身に、かなり焦っていたように思える。
無知であるがゆえに何の思慮も無く思い付くまま、それを行動に移す動物のようなものであったと思う。
そして、それが実は間違っていたり、上手く行かなかったり、また失敗してもそのこと自体“若さの特権”だと自分に無理やり思い込ませることで後ろめたさを封印していたのだ。
何より一番大切な“反省”を怠っていたような気がしてならない。
その頃の私は、ともかく“社長”という思ってもみなかった心地よい称号に空喜びしていたに過ぎなかったと思う。
かく言う“若さの特権”とは、何処でも、何時でも、また誰にでも通用するものではないことを嫌というほど知らされたのもこの頃の1~2年間であった。
その具体例は枚挙にいとまもないが、中でも忘れられないのは暴力沙汰になった件であろう。
私が、岡山県の同業者から社員の引き抜きをし、ある会合の席で、したたかに酔った上で暴力による制裁を受けたという一件だ。
24歳の若さで前歯を含め5本の歯を失った。
私の考えでは、誰もが職業選択の自由があり、勤務先会社選択の自由もまたしかりだと決めつけて、微塵の疑いも持たなかった。
社員の引き抜きにあった会社の社長の思いや怒りなど考えてもみなかったと言えば嘘にはなるが私自身、罪の意識がそれほどあったとは言えなかった。
思えば、労務提供型の仕事において、社員一人ひとりは、その会社にとって最も重要な戦力であり生命線である。
なかんずく、同業者間では暗黙の了解事項として“引き抜き”はご法度である。
やむを得ない場合には、その頃の慣習として会社間のトップ同士で、それ相応のルールの中で仲介者などを入れて話し合いが行われていたようだった。
私はそのような慣習は後で知ることとなるのだが、百歩譲ってその慣習を知らなかったとしても、このような場合、何らかの配慮が必要であろうというごくごく当たり前の常識すら私は知らなかったのである。
それとまだある。
仕事を受注する親会社に対し、同業他社との不公平を至極当然のように抗議したり、ことあるごとに会議などでこれまでの業界体質に異論を発したりもした。
なにしろ、同業他社の社長たちは私の父親くらいの方たちばかりである。
最初は「元気のある若者だ。」くらいに思って下さっていたはずだが、時間が経つにつれて「鼻持ちならぬ若僧」に変わるのは自明の理であった・・・。
それだけに、この頃とりわけ最も気の毒であったのは、当時の社員(15人くらいにはなっていただろうか・・・)たちである。
非常識なリーダーにやむなく従わざるを得ないのである。
間違った指導が多々あったと今になって反省しきりである。
こうして社の内外を問わず、リーダーの無知や成り行きにただ翻弄されるだけの経営に、会社は文字通り不安定さを増すばかりであった。
今、“コンプライアンス”さらには“CSR”という単語が企業経営の有り様の中で重要視されている。
法令遵守、そして 企業の社会的貢献、あるいは企業の社会的責任論など盛んに論議されているようだ。
ここで誤解を恐れず私流に言えば、“コンプライアンス”や“CSR”などの基本的原点は、あらゆる経済活動における企業同士のビジネスライクとは一線を画した“商売道徳”という精神に尽きると考えている。
これが「鼻持ちならぬ若僧」時代に親会社や先輩同業社長たちからのさまざまな形の制裁によって、叩かれながら言いようのない挫折感の中で覚えた教訓である。
私には今もこれからも未来永劫、“商売道徳”の四文字は肌身に染みついている。
余談でこれまた私の独断ではあるが、昨今の企業活動で特に大手企業のリーダーたちに多いが、コンプライアンスやCSRを小手先サイズで吹聴し、あたかもそれを持ってその本質である“商売道徳”のすべてを会得しているかのような錯覚感にはうんざりだ。
それにしても・・・である。よくよく私は頭が悪いし、不器用でもあると思った。
抽象的な言葉ではあるが、“商売道徳”を意識し、覚えこむに至るためには肉体的苦痛が必要であったとは・・・。